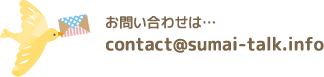「すまいをトーク」は木造住宅を中心に、住まいに関することを建築士を交えて学ぶ会です
次回講座のお知らせ
2026/3/12(木)18:30-20:30
受け継いだ茅葺き古民家再生の記録
→詳細はこちら
<終了しました>
2026/2/19(木)18:30-20:30
知られざるゲタバキ団地の世界
→レポートをアップしました
2025年度スケジュール
2025年度の日程表と各講座の詳細は下記PDFファイルからご確認いただけます。

すまいをトークって?
「すまいをトーク」はどなたでもご参加いただける住まいの勉強会です。受講生は随時募集中、単回参加も大歓迎です!
勉強会内容はスケジュールのページを、受講方法についてはお申し込みとお問い合わせのページをご覧ください。
【第11回レポート】2026年2月19日(木)知られざるゲタバキ団地の世界
団地愛好家集団チーム4.5畳の辻野憲一さんをお迎えして『知られざるゲタバキ団地の世界』をお話しいただきました。
ハンドルネーム「けんちん」さんとして活動されているということですが、その活動や趣味の幅は驚くほど多岐にわたっていて、ご本人も自らを「趣味づくり職人」と称していらっしゃいました。
現在けんちんさんの頭の中を占めているのは、団地、ドムドムバーガー、電気風呂、東横INN、そして閉幕してしまいましたが大阪関西万博とのこと。
趣味には、スポーツや旅行のように自分が主役になるものと、映画や音楽鑑賞など対象が主役となるものに分類されるということです。
長年トランペット演奏を続けてこられているけんちんさんは、その両方のタイプの趣味を楽しまれているんですね。
ひと口に「団地」と言っても、公団(現UR)、公社、公営、社宅の4種類があるそうです。「すまいをトーク」の座学が開催されている建物も、公社や市営住宅に縁がありますね。そして、わたし自身が住んでいるマンションも元公社のものだったので、わたしも団地当事者と言えるかもしれません。
団地の中でも下層階に店舗や事務所が入り、上層階に公的な集合住宅がある形式のものが「ゲタバキ団地」と呼ばれ、市街地で見られます。
ほかにも、オブジェや給水塔、壁画、住棟番号など、団地には見どころがいろいろ。
最近では、建て替えが難しいUR賃貸住宅で、企業とコラボレーションしたリノベーション物件や、住まい手が自分好みにDIYできる住宅も登場し、団地暮らしが改めて注目されています。
けんちんさんの目のつけどころはとてもユニークで、あっという間の2時間でした。
(レポート:運営委員 浜田 綾)
Copyright © すまいをトーク. All Rights Reserved.